2度目のホストファミリーが終了した話
昨年(2024年)6月末から我が家に滞在していた、メキシコからの留学生アールちゃんが、昨日、帰国しました。7か月と少しの、僕たちにとって2度目のホストファミリー生活が終わりました。

鳥取空港で荷物預け入れの手続きをするアールちゃん
アールちゃんは、とても穏やかな性格で、常に周りに対する配慮を欠かさず、自分よりも他人を優先する、とても優しい女の子でした。がゆえに、少し引っ込み思案に映る時もありましたが、秘めている思いや感情はとても強く、頑張り屋さんでした。映画やアニメ、マンガに非常に詳しく、また手先が器用で細かい仕事が得意な彼女は、自分でも絵を描いたり、細部まで作り込まれた見応えのあるプレゼンテーション資料をたくさんつくっていました※1。
アールちゃんがいなくなった我が家、寂しくなりました(が、正直少し違う感情も抱いています。詳しくは最後に)。アールちゃんはマシューのことをすごく可愛がってくれたので、彼もきっと同じように感じているでしょう。
2度目のホストファミリー体験を振り返る
2回しかホストファミリーをやっていない僕たちが偉そうなことは言えないのは重々承知のうえで、まだやったことはないものの興味関心のある方のために、受け入れる留学生と関係を築き、ホストファミリーとしての役割を果たしながらそれを楽しむため、僕たちが何に注意を払い、どう取り組んだのか、何が上手く行き、失敗したのかについて考えてみたいと思います。

アールちゃんが我が家にやって来た時にくれたメキシコの人形
それを書く前に、大前提としてですが、アールちゃんを含め、日本に留学生としてやってくる子供たちのことを、僕は、本当に凄い人たちだと思っています。住み慣れた国、家を離れ、異なる食べ物、気候、言語や慣習を持つ極東の国にやってきて1年近く生活するわけです。この大冒険を自らの選択で踏み出しているんです。その勇気と行動力を、まずは全力で讃えたい。アールちゃんに最大限の敬意を払いながら、彼女の大冒険をホストファミリーとしてどうサポートしていけばいいのか、ひたすら考えた7か月でした。
優先する
仮に自分の子供が海外留学したとします。その留学先、ホストファミリーの父親に自分が憑依できたとしたら、できる限り我が子のことを優先して行動するでしょう。少なくともそこでの生活に慣れるまでは、ちょっと出かけるだけでも付き添ったり、「大丈夫?」と声がけするでしょう。それが良い悪いではなく、親であればおそらく、過保護と思えるくらいにそうする人が多いはずです。留学生に対しても同じようにするべきだと僕は思っています。
自分で選んだとはいえ、まだ10代の若さで、右も左も分からない土地で長い期間、暮らしていくわけです。とてつもない不安とストレスを抱えていることは容易に想像できます。ホストファミリーが自分を受け入れてくれている、自分を尊重し、大切にしてくれていると感じ、いつか彼らがそれを意識しなくなるまで、どんな時でも味方なんだと分かってもらえるまで、時には自分の仕事、都合、家族や子供よりも優先して対応する必要があると思います。
留学生は自分の本当の子供ではありませんが、ホストファミリーは単なる部屋貸し、給仕係ではありません。都合の良い時だけ対応するのではなく、自分の家族と同じように徹底的にコミットすることが、信頼関係を築くうえで欠かせないものだと思います。
話をする
もちろん、何を求め何を求めていないかは留学生によって違います。それゆえに、僕たちはできるだけアールちゃんと話をしました。
今日学校で何があったか、学校の先生やクラスメートたちと何を話したか、何を話せなかったか。困ったことはあったか。面白かったこと、母国との違い、その他気づいたことはあったか。食事の時を中心にいろいろと話をしました。もちろん僕たちも今日のできごとや考えたことを伝えます。
英語での会話※2に参加できない娘は不貞腐れ、自分よりもアールちゃんにたくさん話しかける僕やトム(妻)に対して不満を露わにしていましたが、それも最初の1〜2か月ほど。娘よりも留学生を優先する理由を何度も伝え、日本語でもいいからアールちゃんに色々聞いてあげるよう伝えました。
しかし、思ったことを思ったように伝えられないもどかしさというのは辛いもので、それが毎日続くと、僕たちは自然とそれを避けるようになっていました。最初はコミュニケーションに挑戦しても、徐々に会話は減り、最小限になる。お互いが話しやすく、理解しやすい内容のものだけになってしまう。これはホストファミリー側だけでなく、留学生も感じていることだと思います。
大切なことほど面倒で難しかったりするもの。毎日話をする、これがどれだけ難しく、そして大切なことか、多くのホストファミリーは痛感しているのではないでしょうか。
自分が動く
選ばれてやってきた留学生と聞くと、大人びた学生を想像してしまいますが、彼らは高校生、当然のことながらまだまだ子供の部分も多いです。四六時中スマホを見ているし、必要な連絡を必要な時にできなかったり、黙っていれば朝遅くまで寝ています。まあ、同じようにしている大人もたくさんいるんですが(僕)。
ただ、自分の子供ならば注意する場面であっても、アールちゃんは大きなストレスに対処しながら日本で生活しているわけで、「ここで注意してしまうと、この家での生活がストレスの原因になってしまわないか」と常に自分に問うていました。
ならば注意するのではなく、注意しなくても良い状況や環境をこちらがつくってあげる必要があるのでは……そう気づきました。例えば四六時中スマホを見て(スペイン語の情報にばかり触れて)いるなら、こちらから積極的に話したかけたり、一緒に買い物したり、料理したり、ボードゲームしたり。
「こちらは特に何もしないけど、君はちゃんと生活しなさい」が通らないのは道理。これは留学生云々ではなく、誰に対してもそうではないでしょうか。自分は暇さえあればスマホばかり見ているのに、子供に「勉強しなさい」「本を読む人になりなさい」と言って聞く耳を持ってもらえるはずがないのと同じです。
ストレスが潜むもの
いわゆるフツウの生活を通して日本の文化をアールちゃんに体験してもらう。彼女の留学の大きな目的の一つですが、僕たちホストファミリーにとっては彼女の母国、メキシコの文化を知る貴重な機会にもなります。

和と墨(墨西哥=メキシコ)ミックスの食卓
文化の違いを知ることは楽しい反面、ストレスになる要素も潜んでいます。
分かりやすい話では、ラーメンやそばをズズズーッと音を立てて啜るのは日本の食文化ですが、メキシコでは(というより多くの国や地域では)御法度です。「ここは日本だから音を立てて食べろ」と強制はできません(する気もありません)が、僕はいつもどおり音を立てて食べていました。
また、メキシコでは、くしゃみをした人に対して「¡Salud!(サルー=健康)」と声がけする習慣があります※3。日本を含むアジア圏では、くしゃみした側が「失礼」「ごめんなさい」と周囲に声をかける習慣はあれど、周りが慮ることはありません。アールちゃんは僕たちがくしゃみをしたら「¡Salud!」と声をかけてくれていましたが、僕はそうしませんでした(トムは¡Salud!と声がけしていました)。
こうした小さな違い、日本では良しとされているがアールちゃんの母国ではマナー違反であるもの、当たり前にあるものがないことが、彼女にとってストレスになっていた可能性はあります。しかし、ストレスになるからと言って、彼女のために日本人としての僕の生活を変化させることはしませんでした。
そして彼女に対しても「日本ではこれが一般的」という話はするものの、「あなたもそうした方がいいよ」とは言いませんでした。彼女自身で考えて、日本の文化に合わせて自分の行動を変えるのかそうしないのか、判断することが重要な気がしたからです。
もちろん、日本でやると相手に対して失礼に当たる行為についてはしっかり伝える必要があると思いますが(具体的には思い浮かびませんが、他国の例を挙げると以下のような感じですかね)。
コーカサスでは「人前で足の裏を見せる」って結構なタブーですごく失礼なのだが、エラスムスのドイツ人女がソファーに座って机に足のせてて「そこ他の人も使うとこだしやめな」と言ったら「ドイツでは普通!」とか抜かすので「お前ら何でもドイツは〜とかだから嫌われんだよ!帰れ!」って桜島が大噴火
— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) January 26, 2025
文化の違いについての話を続けると、「リメンバー・ミー」というアニメ映画で有名になった、「死者の日」という風習がメキシコにあります。
日本のお盆によく似ていますが、1週間続くこと※4、思いを馳せる、祈る対象が日によって異なること、毎日祭壇(オフレンダ=Ofrenda)を異なる要素で飾り付けていくことなど、異なる点も多いです。しかし、泉下の客に対する思いを大切にするという、日本とメキシコ双方の文化に通底する共通点を知ることは嬉しいものです。

アールちゃんがつくったオフレンダ。僕たちの祖先や亡くしたペットも混ぜてもらった
それにしても、手作りでオフレンダをつくり、死者の日がどういうものであるかをきちんと説明し、日々これを執り行うアールちゃんを見て感心しました。翻って自分たちは日本の文化を大切にしているだろうか、そう自問自答せざるを得ませんでしたね。
自分の「良い」を押し付けない
先にも書きましたが、アールちゃんは高校生。暇さえあればスマホやタブレットで、SNSや映画を楽しんでいます。
僕のように50歳を過ぎ、人生の終わりを意識せざるを得ない年齢になってくると、残りの時間に何をすべきで何をすべきでないか、ということを常に考えるわけですが、そういう僕からすると、アールちゃんの時間の使い方がいかにも勿体ないと感じてしまいます。
彼女は若く、万能感とともに人生は永遠に続く感覚すら持っている年頃。時間の捉え方が僕と違うのは当然です。しかし、彼女が日本で暮らせる時間というのは確実に有限であり、終わりの日が明確に定まっています。だからこそ、その時にしかできないことを探して取り組んでほしい、日本に来た目的と当初の気持ちを思い出してほしいと考えてしまうんですよね。
しかし他方で、僕たち家族、この家での暮らしに慣れ、溶けこんで、心からリラックスしている彼女の姿を見るのはホストファミリーとしてとても嬉しいものですし、こうした時間も大切なのかなと思ったりもするわけです。
どんな過ごし方をするにせよ、その結果を収穫するのは彼女です。それにこの留学は彼女のものであって、僕のものではない。僕が思う「良い留学」を彼女に押し付けることはできません。
もちろん、「お父さんの考える良い留学とはね…」と2人でカレーらーめん食べながら話しましたが、もしアールちゃんが若い頃の僕ならば、「それなら、お前がそういう留学をしろよ」と返したでしょうね(笑)。
役割
話し合って決めたわけではありませんが、留学生たち(前回のエフちゃん、今回のアールちゃん)と一つ屋根の下暮らす中で、僕とトム、娘、マシューのホストファミリーとしての役割が、各自の個性や能力に応じて自然と決まり、とても機能したように思います。
僕:aw家のルールや大切にしていることをアールちゃんに伝える。日々の注意、指導。学校やAFSとのやりとり、情報共有。事務担当。
トム:一緒に買い物に出たり、美味しいものを食べたり。幸せ担当。
娘:一緒に絵を描いたり、ゲームしたり、アニメを見たり、たわいもない話をしたり。遊び担当。
マシュー:癒し担当。
頭でいろいろ考えて動く大人=僕とトム、無邪気に屈託なく接することのできる娘、無言ながら常にアールちゃんに寄り添うマシュー。とても良いコンビネーションだったんじゃないかな。
アールちゃんが我が家で良い時間を過ごせたとしたら、aw家のチームワークの賜物かと!
本音
アールちゃんが帰国して一夜明けた心境としては、まず「ホッとした」が正直なところです。ホストファミリーとしての責任を果たし切って、なんとか本国のご両親に娘さんを無事にお返しできた、という感じでしょうか。
実際のところ、この7か月は楽しいことばかりではなく、もちろん大変なこともあったし、時間的にも金銭的にも負担がありました。誰もが気軽にできることではないと思います。
しかし、これはトムが言っていたことですが「世界に家族と思える人がいるっていいな」と。本当にそうだなと思いました。
本当の子供でも楽なことばかりではなく、むしろ苦労が多いし、様々な負担もあります。しかし、それでも一緒に時間を紡いでいくからこそ断ちようのない繋がりができるわけで、アールちゃんとの関係もそれと同じ。彼女を本当の家族のように思えるのは、一緒にたくさん苦労したからであり、互いにコミットした結果なのかなと。
だから「ホッとした」の次に来るのは、「やり切った達成感」でしょうか。きっと時間を追って、彼女がこの家にいないことに対する寂寥感が出てくるとは思うのですが。
・・・
最後にアールちゃん、とても楽しい7か月をありがとう。近いうちにメキシコで会いましょう!

- 留学生は、自国のこと、日本での活動などに関するプレゼンテーションを、学校やイベントなどで行うことが多いです
- 我が家に来た当初は、色々と細かい話、内容が間違って伝わってはいけない話が多かったため、英語での会話が多かったのですが、徐々に日本語に軸を移し、後半はほぼ日本語だけでの会話になりました。これも彼女のストレス度合いと日本語の習熟度合いを見ながら、ですね。
- スペインでは、1回目、2回目、3回目のくしゃみに対してそれぞれJesús(ヘスース=イエス)、María(マリーア=イエスの母マリア)、José(ホゼー=ヨセフ)という多少宗教的な習慣があり、ラテンアメリカではSalud(サルー=やぁ)、dinero(ディネーロ=お金)、amor(アモール=愛)となるようです。英語圏では「Bless you!(ブレス・ユー!=祝福があるように!)」、ドイツでは「Gesundheit!(ゲズントハイト!=健康!)」、フランスでは「À tes souhaits ! (ア・テ・スゥエー=きみの思い通りに!)」、オランダでは「Gezondheid!(ヘゾントヘイト!=健康!)」、ポルトガル語圏では「Saúde!(サウーデ!=健康!)」、ロシア語圏では「Будьте здоровы!(ブーッティエ・ズダローヴィ!=健康でいてください!)」と声がけするようです(Wikipediaの内容をawが独自にまとめました)。
- 一般的には10月31日~11月2日の3日間のようですが、アールちゃんが実施していた死者の日は、1週間続くものでした。1日目(10/27)は亡くしたペットや動物たちに祈りを捧げます。2日目(10/28)は最初のろうそくに火が灯され、孤独な魂を迎えるために白い花を捧げます。3日目(10/29)は新たなろうそくに火が灯され、亡くなった人、失踪した人、助けられた人に捧げる水草が飾られます。4日目(10/30)は新しいろうそくに火が灯され、コップ一杯の水と共に白いパンが置かれ、食事を取らずに亡くなった人や事故に遭った人のために捧げられます。5日目(10/31)はろうそくに火が灯され、もう一杯の水、もう1つの白いパン、そして果物が置かれます。これは先祖(曽祖父母たち)のためのものです。6日目(11/1)は「諸聖人の日」で、子供の頃に亡くなった人々の魂である小さな天使たちがやって来る日です。この日にはすべての食べ物が祭壇に並べられます。7日目(11/2)は「死者の日」。亡くなった大人の魂が、家族が祭壇に捧げた供物を求めて現世に帰ってきます。コーパルまたはお香が焚かれ、魂を導くための道がマリーゴールドの花びらで飾られます。8日目(11/3)は最終日。最後の白いろうそくに火が灯されます。コーパルまたはお香に火が灯されます。亡くなった家族の魂に別れを告げ、翌年また戻ってくるように願います。その後、祭壇は取り壊されます。


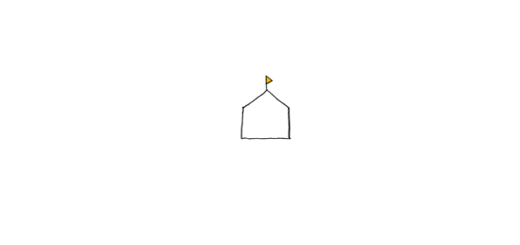

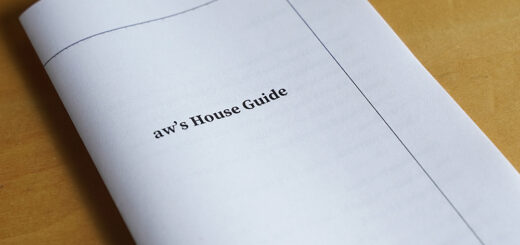




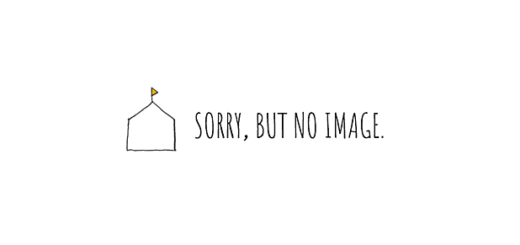



















Hasta la vista アールちゃん
いつかまた日本に来てくれたら、3人でカツ丼弁当食べましょ